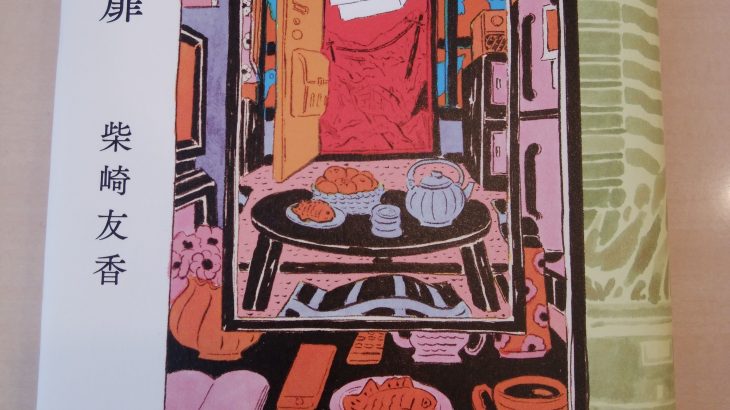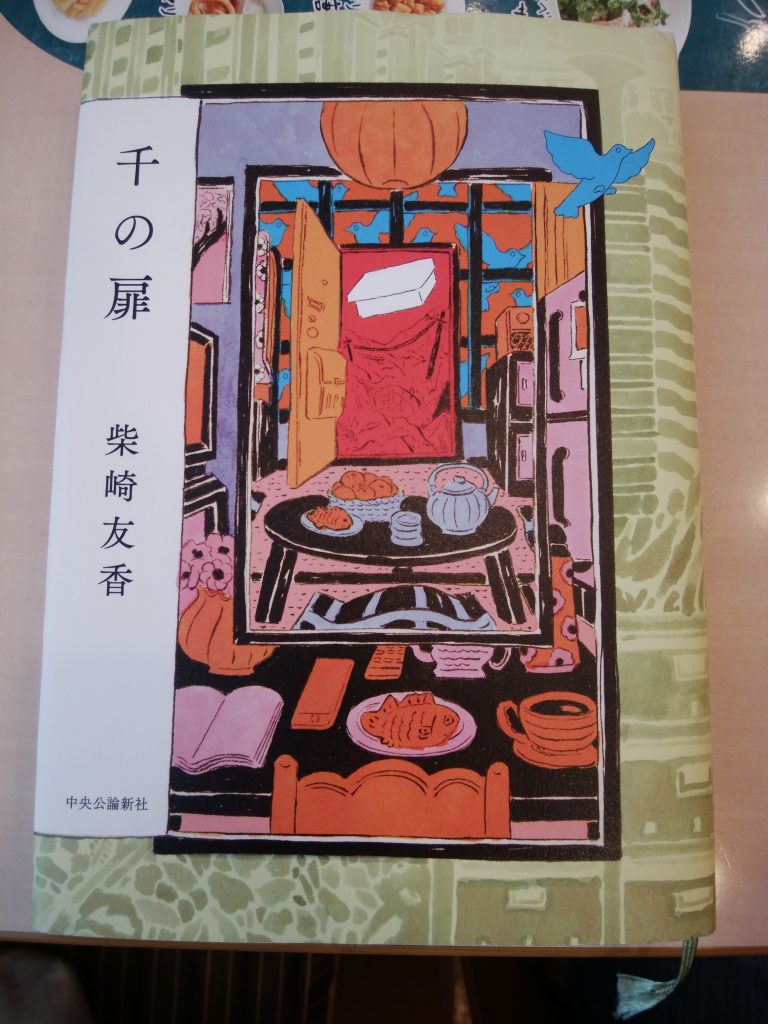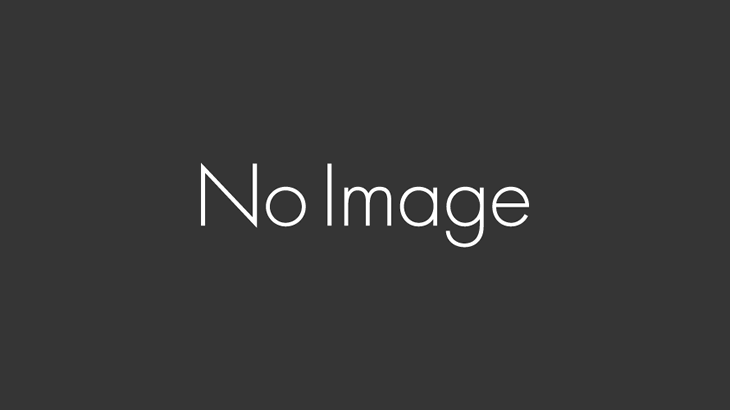柴崎友香 著『千の扉』読了
時間かかったけど、読み終わった。
内容は、団地を舞台に、主人公が義理の祖父の依頼で人捜しをする、というのが大まかなストーリーなんだけど、いわゆるエンタメのストーリー展開ではない。
断片の集合に近い。
団地にまつわる人々の、いろんな時間、場所、視点のエピソードの集合であり、それらは関係あったりなかったり。
文章が、時間も視点も縦横に飛び交うのが、最初は読みづらいと感じたけど、慣れてくるとそうでもなくなった。
小説のつくりとして、明確になにかこれ!っていうメッセージを伝えるようなものではないと思うのだが、しかし読み終わって、これまたなんとも言えない感覚が、確かに想起させられるのだった。
断片、すなわち団地にまつわる人々のエピソードの集合、それらはそれぞれ関係があるようでないんだけど、そうしたことが描かれたこの本は、まさに団地的であるといえるのではないか。
タイトルの千の扉とは、まさに団地を外から見たときの姿ではないか。
なんて思ったのだった。
とはいえ、一回読んだだけなので、改めてまた読んでみたいと思う。
断片の集合といえば
どうしてもこの本のことが思い起こされる。
岸政彦 著『断片的なものの社会学』
去年読んで、自分的にものすごく響いた本。
世界とは、人生とは、無関係で無意味な、断片的なものが集まってできている。
それはエンタメのストーリーのように全てに因果関係があり、要素が連動しているものではない。
けれども、そういったことを示してくれたこの本は、つまらないかといったらそんなことはなく、むしろすごくおもしろい。
そして、内容的に『千の扉』と非常に通じるところがあると見ている。
“関係がない”がある
本質的に、それぞれは関係がない。
しかしながら、“関係がない”ということを、読者である私たちは知ってしまった。
これはつまり、「“関係がない”ことがある」のである。
光を描くために影を描くように、「ない」を描くには「ある」を描く必要があって。
無数の「ある」によって表現された「ない」によって、よくわからないなにか、なんともいえない感覚が、想起されてくるのではないか。
そんなようなことを考えたのだった。
(ほんとはもっと語りたい要素あったけど、ちょっとすぐに語りきれるものでもなかったので、今回はここまで)