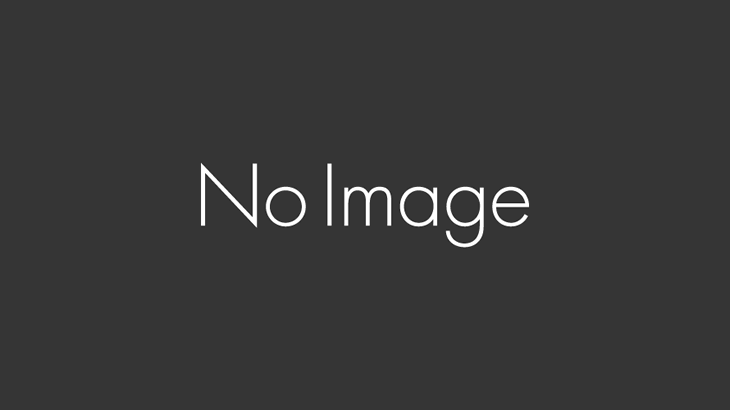ドロシーたちのたそがれ 作・藤川S
その日、彼女は仕事から帰ってくるなり、僕に話しかけたんだ。
「今日会社で健康診断があったんだけど、レントゲン撮ったら、なんと私の胸の中が空っぽだったの!」
あまりに唐突だったから、すぐには理解できなかったよ。
「だから、空っぽなの。何もないんだって。この中」
彼女はふくよかな自分の胸を指差した。
「空っぽって……それは機械が故障していたとか、別の何かが写っていたとかじゃなくて?」
「うん」
にわかには信じがたい話だった。
彼女は、どこかすっきりしたような、さわやかな表情をしていた。久々に見た気がした。最近、彼女は何か悩みを抱えているようだったから。訊いても答えてはくれなかったけど。
「これで原因が分かったわ」
「何の?」
「最近何を見ても、何をしても、何も思わなくなってたの。あなたとご飯食べてもおいしくないし、一緒にTV見てても面白くないし、あなたと出かけても話をしても、何も楽しくないしそれに……」
「えっ、ちょっと、そんなこと思ってたの?」
ショックだったよ。同棲を始めて一年が経っていたけど、僕はうまくいっていると思っていたから。
「大丈夫、あなたが悪いんじゃないわ。悪いのは私のほう。はじめは鬱病かもって思っていたけど、そうじゃなかった。胸の中が空っぽだったからよ」
「どういうこと?」
「だから、心が無くなってたの。だから何も感じなくなっていたんだわ」
「そういえば、このところずっと忙しそうだったからね。まさに心を亡くしてしまったというわけか」
自分ではうまいことを言ったつもりだったけど、彼女は無反応だった。
「まるでブリキの木こりみたいだわ」
「何それ?」
「知らないの?オズの魔法使いっていう物語に出てくるのよ。ブリキでできた人形だから、心を持っていないの」
ほんの一瞬、そんなことも知らないの?と言いたげな、軽蔑するような眼差しを向けられたような気がした。
「それよりどうするのさ。胸が空っぽだなんて」
「お話では、心をもらうためにオズの魔法使いに会いにいくの。だから私も、ここを出て魔法使いのところへ行くわ」
ふざけているのかと思ったよ。
「ちょっと、何を言い出すんだよ。それに魔法使いって何さ」
彼女はもう笑っていなかった。
「私は本気よ。実はその魔法使いにも来てもらってるの。入って」
彼女は部屋の外に向かって声をかけた。扉が開いて、見知らぬ男が現れた。三十代前半くらいの整った顔立ちで、スーツをびしっと着た、なんかいかにも仕事ができそうな、いけ好かない奴だった。
「やあ、どうも。魔法使いとは照れるな」
「だ、誰だ、あんたは」
「小津(おづ)さんっていうの。彼といると胸がいっぱいになって、いろんなことが楽しくて、幸せを感じるの。私にとって魔法使いよ」
「そんな」
それじゃね、と言って彼女は僕に部屋の鍵を放り投げると、オズとかいう男と、うふふあははと笑いながら、部屋を出て行ってしまった。
彼女は僕を捨てたんだ。
僕は半月前の出来事を、友人の鈴木と佐藤に話し終えた。実は彼らも、小津に妻や彼女を寝取られていたのが発覚した。居酒屋に集まって僕らは愚痴を言い合っている。
「気持ちはよくわかるぞ」顔を赤くして鈴木は言った。
「何なんだよ、小津って。意味わかんねぇ」佐藤はビールジョッキを荒々しく置いた
愚痴を言い合っているうち、僕はふと最近読んでみたオズの魔法使いを思い出した。僕らを捨てていった彼女達は、何かが欠けていると思っていた。ブリキの木こりであり案山子でありライオンであったのだろう。さながら僕らはドロシーか?
「小津は魔法使いというより、西の悪い魔女だな」
僕のつぶやきが聞こえたのか、鈴木が言った。
「魔女というより、魔(間)男だろう」
(おわり)